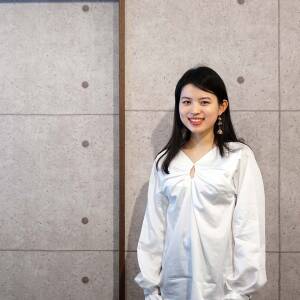2020年8月8日、「コルセットの日」に20年続いた原宿店をクローズし、日本橋で新たなスタートを切ったBaby Doll Tokyo。あらためて、ミラノ氏の人生と共にあるBaby Doll Tokyoの軌跡を振り返るとともに、今後の展開についてたっぷりとお話を伺った。ファンを虜にし続けるミラノ氏とBaby Doll Tokyoの魅力を、3編にわたってお届けする。
「ゾクゾクするもの」に惹かれた子ども時代
━ファンを虜にするBaby Doll Tokyoの世界観。唯一無二のその世界観が生まれた、ミラノさん自身の“原点”はどこにあるのでしょうか?
そうですね、一番はじめの「原点」ということでいうならば、私は、子どもの頃に友だちがいなくて、浮いているタイプだったんです。だから独り、学校の図書館で過ごすことが多くて、その時に目に留まったのが江戸川乱歩の『少年探偵団』シリーズでした。背表紙に黄金の仮面が描かれていたのに惹かれたのでしょう。まだ難しい漢字が読めない低学年の頃でしたが、表紙や挿絵を眺めて過ごしていました。
推理ものや探偵もの、少しグロテスクなもの、盗賊とか変装、変身…、ディズニーで言えば絶対に魔女派ですし、変身願望があったのか、とにかくそうした物語に子どもの頃からとても惹かれました。
きっとそういうことが原点だったと思います。ただ、そういう世界にゾクゾクするという感覚があったとはいえ、それをビジュアルで表現したいという願望にまだ気づいていなかったと思います。
「ダサい!」の一言で火がついた

思春期に、ビジュアル系バンドをやっていた男性と初めてお付き合いをすることになって、彼好みの服装を一生懸命考えてデートに出かけました。お金がないので友だちに洋服を借りたりしながら、頑張って、ゴシックロリータの走りみたいな格好をしてみたり。
それなのに、彼に「ダサい!」と言われたんです。ダサいから、着替えてきて、と。泣いて家に帰りました(笑)。「ダサい」という言葉は、特に思春期の女の子にとっては最悪の言葉です。そのときに絶対におしゃれになろうと決めました。「ダサい!」と言わせない、かっこいいおしゃれを目指そうと。
元々映画も好きでしたし、『CUTiE(キューティ)』や『KERA』などのティーン向けファッション誌を愛読していたというか、夢中になって見ていたので、当時通っていた女子校の家政科にいる友人に「今月のキューティに載っているこの服を、私に合わせて作ってほしい」と頼んだりしていました。雑誌の写真を切り抜いて、さらに自分で直したいところを絵にを描いて、ここを私好みにこうして欲しい、などと注文して。女子学生のオートクチュール(笑)。
田舎のことなので、雑誌に載っているブランドなどどこにも売っていないし、通販も当時はまだ全然なかったので、とにかく自分なりに工夫しなければならない。なんとか似た服を探したり、年に1回ぐらいは、洋服を買うために、母親に大阪まで連れて行ってもらったりもしましたね。
━ファッションに対するこだわりは、ご家族の影響などはあったのでしょうか?
家族の影響というのは最近になってやっと気がつきました。母も、洋服が好きだったんです。もしも交通事故に遭ったりしたとしても、下着だけは恥ずかしくないようにいいものを身につけておきなさいって、わざわざ百貨店まで下着を買いに行ったり。シワのある服を着て外出してはダメとか。他はめちゃくちゃなのですが(笑)、着るものに対してはすごくきちんとしていました。
━美意識が高いお母様だったのですね。
そうですね。料理をしている姿より、いつもアイロンがけをしているような、洗濯とアイロンが上手な母親のイメージ像があります。
“ダサい!”と彼氏に言わせた少女が一変、全国に知られる存在に
━奇抜なファッションをしている中高生は珍しく、好奇の目で見られることもあったのではないですか?
地方のことですから珍しかったですし目立っていたでしょうね。そのおかげで、学区外にも友だちがたくさんできました。
恐らくそういうstyleが好みの方は、好奇の目で見られるのがそこまで嫌ではない人たちかと思います。少なくとも逆に無反応の方がさみしい、と私は感じていました。たとえ他人から「変な格好だ」と言われようと、とにかく自分が好きなカルチャーや世界観に浸っているということが心地よく、ずっと大事なんですよね。
田舎に一軒しかない小さなライブハウスに行くと、自分の身近な家族や人とはなかなかシェアできない自分の「好き、推し」を分かってくれる仲間がいたりする。そのコミューンにいる先輩や仲間は、みんな同じように真っ黒な服を着て、エナメルのヒールを履いて、青色や黒い唇に、爪は緑や青に塗って。一緒に騒いで笑顔になれる。誰も自分の「好き、推し」に否定的な人はいない。
当時そういうカラーのマニュキュアが少なかったのですが、唯一マリークヮントから出ていて、仲間同士で、そのグロテスクなカラーはちょっと引かれるかも?と笑いながらデモーニッシュな色のマリクワのネイルをまるで儀式のように塗ってました。学校があるので髪を染められないので、せめてネイルだけでも!と必死でした。
━ファッションから友だちの輪が広がっていったのですね。
当時『浅草橋ヤング洋品店(のちのアサヤン)』というテレビ番組で、ファッションコンテストのようなものをやっていたのですが、私も友だちが作ってくれた服で参加してみたら、中国地区で優勝してしまったんです。
その後の全国大会ではすぐに落ちてしまったのですが、その理由が「やっぱり黒い服を着ているからあまり良くない」って。それがとてもショックでした。
落ちてはしまいましたが、全国放送で私だけが映っている時間が少しだけあったんです。それが自分で言うのもおこがましいのですが、とても可愛く撮れていたんですよ。それで放送後に全国から「あの番組見ました!」とお手紙をもらったりしました。学校でも、靴箱に手紙が入っていたり。
━それで一躍人気者に。
人気者というより、お騒がせ者でした(笑)。高校では、髪を結ぶリボンが大きすぎると怒られたり、「悪」と書いた服を着てくるんじゃない!と言われたり。その頃から変わらないといえば変わらないですが、今はようやく、まさかの結婚で、旦那さんと子供のおかげで、少し落ち着いた大人になれたような気がします。
初公開!「緑川ミラノ」の誕生秘話、華やかな夜の世界で見えてきたもの

━そんな思春期を過ごされた後、上京、そこからBaby Doll Tokyoのオープンへとつながっていくまでにはどのようなことがあったのでしょうか?
10代の頃に上京して、スカウトされ六本木の高級クラブでバイトをしたのですが、そこは大物芸能人が来るような場所でした。でも、そういうお店で私は全然人気がなかった。ところが「ミラノ」という名前で働くようになってから、なぜかとても人気が出てきたんです。それで、これは私にとってラッキーを運んでくれるな名前だなと思って、大好きな「黒蜥蜴(くろとかげ)*」の緑川夫人から勝手に苗字をもらって、今の「緑川ミラノ」という名前で活動するようになりました。
芸能界の大御所やプロデューサーなどがたくさんくる場所だったので、「オーディションを受けてみない?」などと誘われるようになりましたね。
*「黒蜥蜴(くろとかげ)」:江戸川乱歩の長編探偵小説。宝石等「美しいもの」を狙う美貌の女賊・黒蜥蜴と、名探偵・明智小五郎が対決するストーリー。
━芸能の道を考えたこともあったのでしょうか?
ミラクルなオーディションのオファーをいただき考えたことはありましたが、私はそういう世界で本当に綺麗でおしゃべりも上手な子、その場の空気を変えてしまうほどの存在感、本当に華がある“本物”の子たちをたくさん見てきたので、到底敵わないなと。自信を持てる未来が想像できない(笑)。
それをリアルで見れたことは、六本木で働いていて良かったことですね。
当時から、自分の立ち位置みたいなもの、私は花形の人たちの影になる、黒子になるというのが性に合っているんじゃないかなと思いました。華やかな世界にいながらも、その中では主役でもわき役でもなく、その人たちがより輝けるための「黒子」に回る方が性に合っているなと感じていました。
その後、憧れだったSMクラブでバイトをさせてもらって、その道でも頑張りたいと思ったのですが、女王様になるのはとても難しいんですね。誰でもなれるものではないですし、私にはプロとしての女王様は不向きでした。その人の心の中を支配し快楽の中毒にしていく・・・かなりの想像力とプロとして挑むなら、安全なスキル、テクニックも必要なのですごく難しかったです。
でも、その世界で見たものがとても美しかったし、そこで働いている女性が強く逞しくてとてもチャーミングに見えました。彼女たちと会って話していると、彼女たちに似合う美しいコスチュームやビジュアルイメージがどんどん浮かんできました。
当時の女王様というと、女子プロレスの悪役レスラーみたいな格好しか販売していなかった記憶があります。もっとエレガントで、ヨーロピアンエロスというか、ブラックレースを綺麗にあしらったようなコスチュームがあっても良いのでは?と思っていました。
***
緑川ミラノ氏の知られざる子ども時代のエピソードをお伺いし、Baby Doll Tokyoの原点に迫った今回。次回はいよいよ、Baby Doll Tokyoのオープンからコルセットとの出会い、20年間にあったさまざまなエピソードと、原宿でお店を20年運営してきたミラノ氏の思いについてお聞きする。